・定性調査と定量調査の違い がわかる
・定性調査の種類 がわかる
・定性調査を行う4つのメリット がわかる
・定性調査のやり方(5ステップで手順解説) がわかる
・定性調査を行う際の3つの注意点 がわかる
・定性調査の事例(グッドパッチのご支援事例のご紹介) がわかる
本記事では「定性調査とは何か」について、定量調査との違いや、定性調査の種類・メリット・やり方・注意点・事例などを網羅的に紹介します。
定性調査に関する基本から実践的な手法、失敗を避けるための注意点まで理解できる内容です。定性調査でユーザーのインサイトを的確に獲得し、ビジネスを成長させるために、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
〈グッドパッチにおける定性調査の取り組み事例〉
| 会社 | 概要 |
| 飲食業界の定性調査の事例(三井不動産グループ 株式会社mitaseru JAPAN) | ECサイトやパッケージなどリアルなプロトタイプによるユーザー調査で顧客像と課題を再構築。短期間でサービス設計を具体化し、事業会社設立に貢献 |
| 製薬業界の定性調査の事例 | 通常の分析ではわからなかった、医師の行動・思考の背景を定性調査で深掘りし、マーケティング戦略の土台を構築。社内ワークショップも支援 |
| 医療業界の定性調査の事例(セルソース株式会社) | サービス認知度向上と利用促進のため、医師と患者へのユーザーリサーチを実施し、約20のアクションプランを立案・実施 |
↓【資料DL】グッドパッチの「UXリサーチ3点セット」をご利用ください
目次
定性調査とは
数値化できない「質」的な情報を収集する調査のこと(感情・価値観)
定性調査とは『言葉・行動・感情』などの数値化できない「質」的な情報を収集する調査を指します。「定性調査」では、「はい/いいえ」では答えられない、行動や思考の背後にある「感情」や「動機」「価値観」などを掘り下げる点が特徴です。
例えば、インタビューや観察調査などを通じて、ユーザーが何を考え、何に共感し、どのように行動しているのかを明らかにします。定性調査はアイデアのネタを見つけたいときや、ユーザーインサイトを得たいケースに適した調査です。「インサイト(Insight)」とは「本質的なニーズ・課題とその背景となる状況・価値観・考え方への洞察」を意味するUXリサーチの言葉です。
UXデザインにおける定性調査の実施目的(ビジネスゴールとユーザーゴールの橋渡し)
UXデザイン(ユーザー体験設計)における定性調査の実施目的は「ビジネスゴールとユーザーゴールの橋渡しをする」ことです。具体的には「より良いサービスデザイン設計のためのユーザー理解」を進める目的で実施されます。
例えば、「売上を上げたい」という企業側の目的と、「ストレスなく使えるサービスを使いたい」というユーザー側の期待があるとします。この両者のゴールをつなげるためには、表面的なニーズではなく、背景にある心理や価値観を理解しなければなりません。
定性調査ではインタビューや行動観察、日記調査などを用いて、ユーザーの声を丁寧に拾い上げます。調査から導かれるインサイトはサービスの土台を築く材料となり、ビジネスの意思決定にも説得力を持たせます。
最終的には定性調査と定量調査から得られた情報を組み合わせて、物事を多角的・複合的に捉え、新たな顧客ニーズの探索や商品・サービス改善の仮説検証を進めていきます。これらのユーザーを理解するための調査全体を「UXリサーチ」と呼びます。
「UXリサーチ」や「定量調査」については、以下の記事で詳しく解説しています。併せて確認してみてください。
【関連記事】【保存版】UXリサーチ完全ガイド|成功のポイントと手順を徹底解説
【関連記事】定量調査はここから始めよ ファクトベースでグロースを進める「プロダクトアナリティクス」入門
定性調査と定量調査の違い
定性調査と定量調査の違いが分かる一覧表
| 項目 | 定性調査 | 定量調査 |
|---|---|---|
| サンプル数 | 少人数(数名〜数十名) | 多人数(数百〜数千名) |
| 代表的な例 | ・グループインタビュー ・デプスインタビュー ・エスノグラフィ |
・Webアンケート ・アクセス解析 ・ABテスト結果分析 |
| 特徴 | 深い理解・気づき・インサイトを得る | 数値的な傾向や相関を把握する |
| 得られる情報 | 感情・価値観・動機・課題の背景 | 認知率・満足度・行動量などの指標 |
| おすすめのケース | ・課題解決のためのアイデア・ヒントの発見 ・仮説の構築 ・顧客のニーズの深掘り ・事実の背景や原因調査 など |
・仮説の検証 ・市場の実態/傾向の把握 ・満足度や認知率などの確認 ・キャンペーンや広告の効果の測定など |
定性調査と定量調査の違いは上表の通りです。定性調査と定量調査では「特徴・得られる情報・おすすめのケース」が異なるため、目的に応じて適切に使い分けることが重要です。
定性調査は定量調査と組み合わせることで効果を高める
「定性調査と定量調査は組み合わせて利用する」ことで効果を高めることができます。「定性調査で仮説を構築し、定量調査でその仮説を検証する」といったふうに両者を組み合わせることで、精度の高いリサーチを実現します。
定性調査と定量調査のどちらか片方だけを実施しても、確度の高い仮説検証には届きにくいものです。例えば、定量調査で得られた「数値の変化」のみを見ているだけでは、その背景にある理由を理解できず正しい施策に結びつきません。一方で定性調査の結果だけを利用する場合だと、調査対象が少人数に限られるため、得られた示唆が母集団全体に当てはまるかの判断が困難です。
特にプロダクト開発やサービス改善の現場では、定性調査と定量調査を組み合わせたリサーチ設計が欠かせません。
定性調査と定量調査の組み合わせについては以下の記事でも紹介していますので、ぜひ確認してみてください。
【関連記事】定性と定量を融合したリサーチでユーザーインサイトを探る方法
【関連記事】確度の高い仮説検証を実現する「定性×定量 二刀流」のススメ
定性調査の種類
| 調査の種類 | 概要 |
|---|---|
| インタビュー | ユーザーから直接話を聞く形式の調査。1対1で行う「デプスインタビュー」や、複数人で行う「フォーカスグループインタビュー」がある |
| 行動観察調査(エスノグラフィ) | ユーザーの日常的な環境下での行動を観察し、無意識の行動や潜在的なニーズを発見する |
| 訪問調査 | ユーザーの自宅や職場などを直接訪問し、生活環境全体の中でインタビューや観察を行う |
| 日記調査 | 一定期間、ユーザーに行動や感情などを日記形式で記録してもらう |
| 共創ワークショップ | 参加者(ユーザー)と事業者が一緒に課題解決やアイデア創出を行う「共創型」の手法 |
| MROC(オンラインコミュニティ調査) | 限定されたオンラインコミュニティ上で、参加者と継続的にコミュニケーションをとり、意見などを収集する |
| ミステリーショッパー(覆面調査) | 調査員が一般顧客になりすまし、店舗やサービスを実際に利用して接客や提供品質などを評価する |
これらをはじめ、定性調査の種類にはさまざまな手法があります。ここでは、UXリサーチやマーケティングの現場でよく活用される調査手法について、詳しく解説します。
インタビュー
| インタビューの種類 |
|---|
|
インタビューは「ユーザーから直接話を聞く形式の調査方法」です。
行動の背景や感情、価値観を引き出すための代表的な手法といえます。特に深い気付きを得たいときには、個人の体験にじっくり向き合えるインタビューが有効です。
インタビューの種類には「デプスインタビュー」と「フォーカスグループインタビュー」が存在します。
デプスインタビュー
デプスインタビューは「基本的に調査員と対象者の1対1で実施されるインタビュー」です。
デプスインタビューは1対1のインタビュー形式を取るため、表面的な回答ではなく「なぜそう思ったのか」「どんな経験が影響しているのか」といった深層心理が掘り下げやすいという特徴があります。
他人を意識することなく話せる環境を整えることで、本音や無意識の考えが引き出しやすくなりますので、実施時にはこの点を意識してみましょう。
フォーカスグループインタビュー
フォーカスグループインタビューは「5〜8名程度の複数人で行う座談会形式のインタビュー」です。
フォーカスグループインタビューを実施することで、質問に対する回答が得られるだけでなく、参加者同士の会話の中で意見が広がったり、思わぬ気づきが生まれるメリットが得られます。
個人の深掘りができるデプスインタビューと比較して「多角的な視点や共通認識の収集」に向いているインタビュー形式と言えます。
【関連記事】UXデザインにおけるユーザーインタビューとは?方法・種類・実例ノウハウ集
行動観察調査(エスノグラフィ)
行動観察調査(エスノグラフィ)とは「ユーザーの日常行動を観察し、無意識の行動や潜在的なニーズを見つけ出すインタビュー」です。
行動観察調査(エスノグラフィ)では、サービスや製品の利用シーンに実際に立ち会い、ユーザーの行動に潜む課題を可視化することを目指します。聞き取りでは見えない、リアルな使用実態を把握したいときに向いています。
エスノグラフィについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せて確認してみてください。
【関連記事】ユーザー調査で「行動観察」、せっかくやるなら「リアリティ」にこだわろう
【関連記事】ユーザーの生活に深く潜り込む、エスノグラフィで大切にしたいマインドセット
訪問調査
訪問調査は「対象者の生活や仕事の場を直接訪問してインタビューや観察を行う定性調査手法」です。
ユーザーの暮らしの様子や環境も含めて理解できるため、生活全体の文脈の中でユーザー行動を読み解きたいときに有効です。
日記調査
日記調査は「一定期間の間、ユーザー自身に行動や感情を記録してもらう定性調査手法」です。
インタビューでは拾いきれない時間軸での変化や、継続的な利用実態を把握することができます。長期的な体験の推移や、心理の変化を追いたい場合に向いています。
【関連記事】徹底的な顧客理解が事業化実現の鍵に——三井不動産グループの厳選お取り寄せグルメサービス「mitaseru(ミタセル)」のPoC支援
共創ワークショップ
共創ワークショップは「参加者と一緒に課題解決やアイデア創出を行う『共創型』の定性調査手法」です。
共創ワークショップを利用すると「一方的なヒアリングではなく参加者自身が思考しながら意見を交わす」ことができるため、より具体的で実行可能な気づきの獲得につながります。
MROC(オンラインコミュニティ調査)
MROC(オンラインコミュニティ調査)は「参加者をクローズドなオンライン環境に招き、継続的に行動や意見を収集する定性調査手法」です。
長期的な視点から得られる「変化」や「生活実感」を記録できるため、新しい価値観や深層的な態度変化を探る場合に役立ちます。
ミステリーショッパー(覆面調査)
ミステリーショッパーは「覆面調査」とも呼ばれる定性調査手法です。調査員が一般の顧客になりすまして店舗やサービスを利用し、一連の体験を評価します。
現場で実際に何が起きているのか、提供側が把握できていない課題を明らかにするのにおすすめの調査手法です。
定性調査を行う4つのメリット
ここからは「定性調査の利用メリット」を解説します。
1.数字では表せないユーザーの動機や心理を深掘りできる
定性調査を行うメリットの1つ目は「数字では表せないユーザーの動機や心理を深掘りできる」ことです。定量調査では「なぜ?」というユーザー行動の背景を、「ユーザーとの対話や観察」を通じて明らかにできます。
例えば「なぜこの機能を使わなかったのか?」という問いに対し、数値では見えない「操作が不安だった」「期待していた体験と違った」などの具体的な内面を知ることが可能です。行動の理由を構造的に理解できるため、課題の本質に迫るヒントが得られます。
2.潜在ニーズの発見やインサイトの獲得ができる
定性調査を行うメリットの2つ目は「潜在ニーズの発見やインサイトの獲得ができる」ことです。
定性調査を実施すると、ユーザーとの対話の過程で本人も意識していなかった「不満」や「隠れた欲求」が明らかになることがあります。このインサイトを正しく獲得することで、本質的な課題や価値が浮かび上がり、ユーザーの深層ニーズに応えられる魅力的な体験や機能の設計が実現します。
特に「サービスの企画段階」や「新たなアイデアの模索プロセス」において、潜在ニーズやインサイトの獲得は精度の高い仮説を立てることに役立ちます。
【関連記事】顧客インサイトとは?メリット・見つけ方・フレームワーク・分析方法・注意点・成功事例まとめ
3.ユーザーのリアルな言葉や行動が得られる
定性調査を行うメリットの3つ目は「ユーザーのリアルな言葉や行動が得られる」ことです。
定性調査を実施すると、アンケートの選択肢では拾いきれないような「リアルな声」や「具体的なエピソード」を収集できます。ユーザーが日常で使っている言葉や、実際にどのようにサービスを利用しているかといった生の情報は、プロダクトやコンテンツの改善につながります。
調査対象者の声をレポートに反映すれば、資料作成やチーム内での共有にも役立ちます。ユーザーの具体的な言葉や行動は「プロダクト改善の質を高める貴重な情報源」となるでしょう。
4.施策に説得力が出る
定性調査を行うメリットの4つ目は「施策に説得力が出る」ことです。
ユーザーの具体的な声やエピソードは、数値データだけでは伝わりにくい「共感」や「納得感」を生みます。
ユーザーの具体的な声をもとにした提案は「関係者への説明」や「意思決定の際に強い根拠」となります。社内での合意形成に課題を抱えているチームにとって、ユーザーの声はプロジェクト推進の武器となるはずです。
定性調査のやり方(5ステップで手順解説)
ここからは「定性調査の基本的な進め方」を5つのステップに分けて解説します。
1.調査企画の設計とゴールを設定する
定性調査の1つ目のステップは「調査企画の設計とゴールを設定する」ことです。定性調査を通じて、何を明らかにしたいのかを明確にしましょう。
例えば「サービスの使いづらさの原因を知りたい」「購入までの意思決定プロセスを深掘りしたい」などのように、調査企画の目的を具体的に定義します。
対象者の条件も「性別・年代」などの属性情報だけでは不十分です。「どういう使い方をしているか」「どんな課題を感じているか」などの行動・心理ベースで整理することで、より本質的な定性調査に近づきます。
2.対象者をリクルーティングする
定性調査の2つ目のステップは「対象者をリクルーティングする」ことです。調査の目的に合った対象者を見つけ出しましょう。顧客リストの活用に加えて、SNSや紹介、調査会社などを通じてリクルーティングすることが一般的です。
リクルーティングの際は「調査目的と照らし合わせて、最適な対象者をリクルーティングできているかどうか」を軸に判断することが重要です。「対象者の行動や体験が何かを教えてくれそうか」という視点を持つと、質の高いインタビューにつながります。
3.聞くべきことを整理する
定性調査の3つ目のステップは「聞くべきことを整理する」ことです。定性調査を行う前に、ゴールにたどり着くために必要となる情報を整理して、会話の流れをデザインします。
例えば、以下のような工夫を取り入れると効果的です。
- はい/いいえで終わらないオープンエンドな質問を使う
- 過去の具体的なエピソードを聞く
- 繰り返し問いを重ねる「ラダリング法」を意識する
会話の流れを事前にイメージして設計しておくと、調査の質が向上します。
4.調査を実行する
定性調査の4つ目のステップは「調査を実行する」ことです。
調査の現場では「対象者が安心して話せる空気づくり」が重要です。調査員は「教えてもらう姿勢」で臨み、共感の相槌や適度な沈黙を生かしながら、丁寧に話を引き出しましょう。
インタビューでありがちなミスとして、「質問票通りに進めすぎる」「答えを急かしてしまう」といったケースが挙げられます。流れに縛られすぎず、相手の語りを受け止めながら柔軟に対応することもポイントです。
5.データを分析しインサイトを導き出す
定性調査の5つ目のステップは「データを分析しインサイトを導き出す」ことです。
定性調査で得られた情報をもとにインサイトを導き出します。インタビューの発言をまとめるだけでなく、「なぜこのような傾向があるのか」といった構造的な理解に落とし込み、深掘りしましょう。
良いインサイトは「事業やプロダクトに新たなアクションをもたらす」ものです。得られた情報はチームで共有し、意思決定に活かせる形になるまでブラッシュアップを重ねましょう。
定性調査を行う際の3つの注意点
定性調査は深いユーザー理解を得る上で有効な手法ですが、進める際にはいくつか気をつけたいポイントがあります。調査実施時に意識したい3つの注意点を紹介します。
1.ニーズの確度が低いまま施策を進めないこと
定性調査を行う際の注意点の1つ目は「ニーズの確度が低いまま施策を進めないこと」です。定性調査では深い気づきが得られる一方で、「必ずしも全体の傾向を代表しているとは限らない」という点に注意が必要です。過度に少数のサンプル結果に依存すると「実際の市場ニーズとズレた施策に投資してしまうリスク」があります。
実際の市場ニーズとのズレを防ぐには「定性調査と定量調査のデータ併用」が有効です。定性調査で得られた仮説やインサイトの正確性を、定量調査や既存のデータなどで検証しましょう。
2.独自の仮説に依存しすぎないこと
定性調査を行う際の注意点の2つ目は「独自の仮説に依存しすぎないこと」です。調査設計や分析において、最初に立てた独自の仮説に合致する発言ばかりを拾ってしまう場合があるため注意すべきです。
独自仮説に依存してしまうと、定性調査結果が「仮説の強化材料」としてのみ機能してしまい、新たな視点や発見を阻害してしまう恐れがあります。意識的に「仮説に合わない声」にも耳を傾ける姿勢を心がけましょう。
3.成長に直結しないKPIに固執しないこと
定性調査を行う際の注意点の3つ目は「成長に直結しないKPIに固執しないこと」です。定性調査では多くの場合「数字にならない情報」を扱います。定性調査結果を既存のKPIに無理やり当てはめようとすると、本来獲得すべきインサイトを見落とすことがあるので注意すべきです。
施策の意図とKPIがずれている場合は、思い切ってKPIそのものを見直すことも検討しましょう。KPIはあくまで「行動を促すための指標」であり、インサイトを無視してまで守るべきゴールではありません。
定性調査の事例(グッドパッチのご支援事例のご紹介)
| 会社 | 概要 |
| 飲食業界の定性調査の事例(三井不動産グループ 株式会社mitaseru JAPAN) | ECサイトやパッケージなどリアルなプロトタイプによるユーザー調査で顧客像と課題を再構築。短期間でサービス設計を具体化し、事業会社設立に貢献 |
| 製薬業界の定性調査の事例 | 通常の分析ではわからなかった、医師の行動・思考の背景を定性調査で深掘りし、マーケティング戦略の土台を構築。社内ワークショップも支援 |
| 医療業界の定性調査の事例(セルソース株式会社) | サービス認知度向上と利用促進のため、医師と患者へのユーザーリサーチを実施し、約20のアクションプランを立案・実施 |
最後に、グッドパッチが実際にご支援した「定性調査の事例」を紹介します。定性調査の具体的なプロセスを知ることで、自社で活用する際のヒントにもなるはずです。
1.飲食業界の定性調査の事例(株式会社mitaseru JAPAN)
 出典:株式会社グッドパッチ | Work「mitaseru(ミタセル)」
出典:株式会社グッドパッチ | Work「mitaseru(ミタセル)」
事業案をさらに磨き込むため、お取り寄せグルメを運営するmitaseru JAPANは「ユーザーが本当に求めている食体験とは何か」をより深く探求したいと考えていました。
mitaseru JAPANのご依頼を満たすため、グッドパッチは日記調査や密着調査などを通じて、ユーザーの食に対する価値観や背景にある日本文化への理解を深めました。リサーチを基に、サービス価値やユーザーセグメント、ユーザー体験設計などのアップデートを行っています。
プロトタイプを用いた定性調査では、商品の配送から解凍、盛り付け、後片付けまでの一連の体験すべてがサービスの価値に含まれるという重要な発見がありました。単なる「冷凍食品の販売」ではなく、「顧客体験全体を重視したサービス」へと提供価値の方向性が明確になったのです。
上記のような「顧客への深い理解に基づいた事業計画」は、三井不動産社内での事業化承認に置いても重要な役割を果たしています。約2年間の検証期間を経て、2024年4月に事業会社設立という成果にもつながりました。(※同社ではグッドパッチの支援内容をベースとした「リサーチの内製化」にも成功しています)
三井不動産グループの事例について詳しくは、下記の資料をダウンロードしてご覧ください。
2.製薬業界の定性調査の事例

グッドパッチの製薬業界における定性調査事例では、「医師の情報収集に関する定量調査だけでは分からない『行動』や『思考』の背景を明らかにし、実態に即したアクションにつなげた定性調査の事例」があります。
ある製薬会社では「デジタル化やコロナ禍による医師の行動・思考の変化」を感じていました。定量調査を定期的に実施していたものの、その数値の裏側にあるインサイトをより深く理解し具体的な施策につなげるための別アプローチを模索していました。
そこでグッドパッチは「医師のリアルな情報収集行動の実態を明らかにするための定性調査」を実施。この定性調査の結果に基づき「医師視点のUXを加味したデジタル・マーケティング施策の方向性」を検討しました。
定性調査から得られたインサイトは、オンライン・オフラインを横断するマーケティング戦略全体の土台として現在も活用いただいています。施策を推進する担当者向けにもワークショップを開催し、調査結果から得られた「医師への深い理解」を組織全体に浸透させる支援も行いました。
3.医療業界の定性調査の事例(セルソース株式会社)
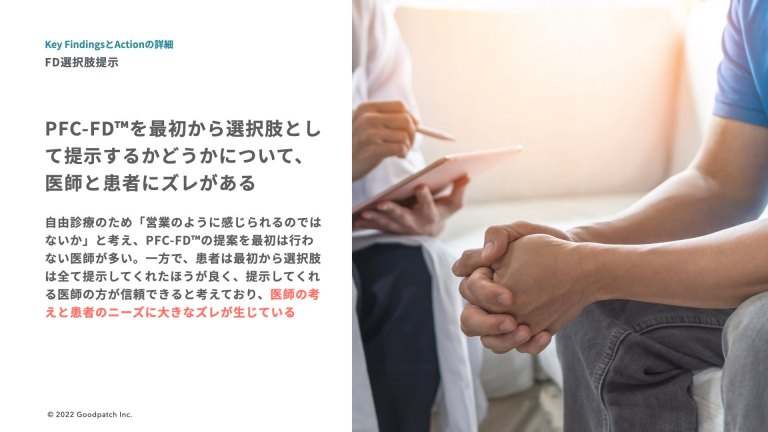
出典:医療現場のインサイトを獲得し、PFC-FD™療法を届けるための認知ギャップを探る。セルソースとのリサーチプロジェクト
再生医療関連事業を展開するセルソース株式会社は「事業のさらなる成長を目指し、共通の営業戦略を模索」していました。現場からは多くの施策案が上がっていたものの、課題の全体像や根拠が明確でなかったため、投資すべき施策の優先順位を判断することが難しい状況でした。
グッドパッチは医師と患者双方への定性調査を実施し、「課題の全体像」と「両者の間にある認識のギャップ」を明らかにすることから支援を始めました。
調査の結果、医師は「保険適用外の治療を勧めると患者が離れてしまう」と懸念する一方で、患者は「費用にかかわらず、すべての治療選択肢を知りたい」と考えているという、重要なインサイトが浮かび上がりました。そこでインサイトを基に現場メンバーを巻き込んだワークショップを開催。認識のズレを解消するための具体的な施策を検討し、約20もの行動計画が策定されました。
策定したアイデアを「インパクトの大きさ」と「実現のしやすさ」で評価し、優先度の高いものから実行に移すスケジュールを設定。
定性調査によってユーザー(患者)の声を直接聞くことが、既存の枠組みを超えた新しいアイデアの創出につながり、具体的なアクションプランへと結実した事例です。
セルソース株式会社の事例についての詳しい解説は、下記のアーカイブ動画でご覧ください。
定性調査の効果を最大化するならグッドパッチ
本記事では「定性調査とは何か」について、定量調査との違いや、定性調査の種類・メリット・やり方・注意点・事例など網羅的に解説しました。
定性調査は「数字では表せないユーザーの動機や心理」を深掘りできることがメリットです。しかし、自社に定性調査のノウハウがない場合、どのように進めてよいかわからないケースも多いでしょう。
グッドパッチでは、デザインの技術を活かして事業戦略の立案から立ち上げまでを広く支援しています。「自社にあったリサーチ手法が分からない」「具体的にどう定性調査を進めれば良いかわからない」など、お悩みに合わせてご支援します。
コミット力が高く、熱量のあるパートナーをお探しの方は、ぜひグッドパッチまでご相談ください。